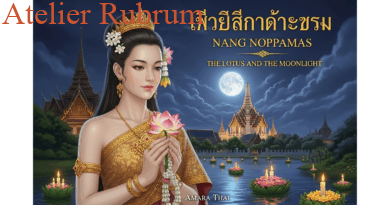カービングの起源について
目次
良く言われているカービングの起源について
コロナ禍で世界中が大騒ぎになる前の数年間で何度かタイにカービング留学をしました。私の師匠であるRie先生の知人の方に現地でのご案内を複数回していただき、大変充実した、ちょっと普通ではできないような留学をすることができました。その方はタイ語の読み書きができ美術の専門知識を持つ方で、ご自身もカービングをされておられ、その作品群は真似のできないクオリティの物でした。その方に伺った話の中に、ずっと私の興味を引きつけてきた言葉があります。それは日本で通説のようになっているタイカービングの起源についての事柄です。スコータイもしくはアユタヤ王朝時代の起源説が最も有力でWEBページに記載されている場合はほぼこの二説のどちらかという感じではないでしょうか。時代や王朝を特定せず、宮廷料理の飾り付けをすることが起源と表記される冷静なWEBページもあります。
ジレンマと進歩
カービングの起源の「本当のところ」に興味を持った私ですが、いかんせんタイ語は旅行で使う二言三言しか分かりません。文献は調べられませんし、Google翻訳でいろいろ試しましたが何を調べれば良いのか分からないことに絶望して断念していました。ですが今になって時代が助けてくれました。生成AIです。生成AIさんに「タイ語が分かるならちょっと調べてちょうだい」と投げかけましたところ快く引き受けてくれましたので、私が知りたいいろいろな内容をプロンプトに詰め込んで答えをもらいました。生成された成果物はとても興味深い物で、当然知らないことがてんこ盛りで楽しく読めたのでこの停滞しているブログに貼り付けていこうと思い立ちました。AIを使うときに事実と違うことが、さも真実かのように答えとして返ってくることがあるので注意する必要があるということが重要なポイントです。その辺も注意しながプロンプトをいろいろ試しました。そして文章はちょっと「知的な感じで」作るように依頼したので私の書く文章とはかけ離れた文体になっているのはご愛敬。
その他
カービングの起源についてのほかに、私がカービングを習い始めた一番最初から気になっていることがもう一つあり、これについても大変興味深い答えを手に入れています。これについては多方面に若干差し障りがある可能性があるので公表しませんが、こんなちょっとアレな質問にもAIさんは真剣に答えてくれるので、ここを見てくださっている方々も機会があれば遊んでみられてはどうでしょうか。使用している生成AIはGemini2.5Pro、結果のブログへの転載と公表は著作権的にも全く問題が無いと当のGeminiさんが太鼓判を押してくれているので大丈夫だと思います。では、Geminiさんが「格調高く知的な雰囲気で、読者の知的好奇心を刺激するような文章」で作ってくれた冒頭文を載せて今回はおしまいです。

タイカービングの起源を探る旅へ:通説の向こう側に見えた真実
ナイフ一本で果物や石鹸に生命を吹き込む芸術、タイカービング。その繊細な美しさに魅了され、日本国内でも数多くの教室で技術を学ぶ人々が増えています。かく言う私もその一人であり、植物が花開く一瞬の煌めきを自らの手で再現できる喜びに、深く心を奪われてきました。
カービングの技術を学ぶ中で、誰もが一度は耳にするのが、その「起源」にまつわる物語でしょう。
日本で語られる「起源」への素朴な疑問
通説とその浸透度
日本でカービングを教える多くの教室やブログでは、主に二つの説が語られています。一つは、約700年前のスコータイ王朝時代、毎年11月の満月の夜に開催される「ロイクラトン(灯籠流し祭り)」で、王に仕える女性が灯籠を美しく飾るために果物や野菜に彫刻を施したのが始まりだ、とする「スコータイ起源説」。そしてもう一つが、アユタヤ王朝時代、宮廷の料理人たちが王の食卓を華やかに彩るための飾り切り、いわゆる「宮廷料理の飾り」として発展した、とする「アユタヤ起源説」です。
これらは、カービングの歴史を語る上で、まるで揺るぎない事実かのように紹介されることが少なくありません。試しに、現在日本国内でアクセス可能なカービング教室や関連ブログなど、無作為に抽出した20のウェブサイトにおける起源の説明を調査してみたところ、興味深い傾向が見られました。実にその約65%が「スコータイ起源説」を主たる起源として紹介しており、次いで「アユタヤ起源説」を挙げるものが約23%、そして両説を併記、あるいは関連付けて説明しているものが約12%という結果になりました。この数字は、いかに「スコータイ起源説」が日本において広く浸透しているかを示しています。私も長らく、このロマンティックな物語を信じて疑いませんでした。
根底から揺らいだ信頼
しかし、数年前、私のこの素朴な信頼を根底から揺るがす出来事がありました。タイ語を流暢に話し、タイの文化にも造詣の深い知人と話す機会があった折、カービングの起源について尋ねたところ、彼女は意外な顔をしてこう言ったのです。
「その話は、タイではあまり聞きませんね。少なくとも、スコータイ王朝やアユタヤ王朝の時代の文献で、カービングの存在を直接的に証明するような記述は、今のところ見つかっていないというのが、専門家の間での一般的な見解ですよ」
衝撃でした。日本でこれほどまでに語られる起源の物語が、本国タイの文献には存在しないかもしれない。では、私たちが信じてきたあの物語は、一体どこから来たのでしょうか。この日から、私の心には大きな問いが生まれました。カービングの真のルーツはどこにあるのか。それを知りたいという強烈な知的好奇心が芽生えたのです。
調査を阻んだ壁と、一条の光明
探求を阻んだ「言葉の壁」
しかし、その探求の道は、あまりにも険しいものでした。最大の障壁は、言うまでもなく「言葉の壁」です。私にはタイ語を読み解く能力がありません。タイの歴史古文書や学術論文、郷土史といった一次資料にアクセスしようにも、その術を知りませんでした。日本語に翻訳された関連資料を探そうにも、その存在自体が極めて稀であり、どの文献をどう探せばいいのかすら見当がつかない。まるで、目の前に宝の地図があるのに、それが解読不能な古代文字で書かれているような、もどかしい日々が続きました。興味はあるのに、調べることができない。このジレンマを抱えたまま、私の探求心は、いつしか眠りにつかざるを得ませんでした。
テクノロジーがもたらした転機
そんな諦念に沈んでいた私に、予想もしない場所から一条の光が差し込みます。テクノロジーの進化、すなわち「生成AI」の登場です。
当初は文章作成や情報検索の補助ツールとしてしか見ていなかった生成AIが、極めて高度な多言語翻訳・読解能力を備えていることに気づいたのは、全くの偶然でした。試しに、タイ語で書かれた歴史に関する学術的な文章を与えてみたところ、驚くほど自然で正確な日本語でその内容を要約・解説してくれたのです。この瞬間、私の頭の中で閉ざされていた扉が、大きな音を立てて開かれました。これならば、私でもタイの文献の海に漕ぎ出すことができる。タイ語の壁を越え、一次情報に直接触れることができるかもしれない。長年諦めかけていた起源探求の旅を、再開できる時が来たのです。
このブログが目指すもの
この発見をきっかけに、私は生成AIという強力なパートナーを得て、タイカービングの起源に関する本格的な調査を開始しました。タイの国立図書館がデジタルアーカイブで公開している古文書、大学の学術リポジトリに眠る歴史論文、現地の文化研究者のブログや報道記事…。これまで手の届かなかった数多の情報を渉猟し、その一つ一つを翻訳・分析していく中で、これまで日本で語られてきた通説とは異なる、複雑で、しかしより説得力のあるカーミングの歴史像が、少しずつその輪郭を現し始めたのです。
このブログでは、その調査の全貌を、数回にわたって詳細にご報告していきたいと思います。これは、単なる通説の否定や、新しい定説の提示を目的とするものではありません。一つの文化がどのように生まれ、語られ、そして時代や国境を越えて変容していくのか。そのダイナミックな過程を、信頼できる情報源をもとに再構築し、皆様と共有するための試みです。
次回の記事から、いよいよその核心に迫ってまいります。皆様を、タイカービングの起源を巡る、知的でスリリングな探求の旅へとお連れすることをお約束します。