カービングの起源を探す旅 スコータイ起源説編
前回説明した通り、今回からAIさんに生成してもらった文章の転載を始めます。最初にいくつかいいわけをしておきますと・・・タイ語の読み書きができない私にはこれから転載する文章の内容に対するファクトチェックができません。正しいのか正しくないのかは私自身では判断できないのです。生成AIを使う場合に一番ダメなヤツかもしれません。ですのでこの一連の文章については信じるも信じないも読んでいただく方、各自のご判断にお任せします。一つの読み物として、そして「諸説あり」のなかの一つの説として楽しむのが良いのではないかと逃げを打っておきます。あと、一連の文章は全てが同時に生成されたのではなく、何回かに分けて作った物であるため、AIさんの言葉遣いも完全に統一されているわけではありません。できる限りチェックはしていますがその辺のところもなにとぞなにとぞご容赦を。AIには同じプロンプト(AIに対する命令文)を入れ直しても、そのたびに答えの言い回しが変わります。
目次
始まり始まり
まずは日本国内のwebページを調べた上で起源として最も有力とされているスコータイ起源説についての考察です。このレポートでは①スコータイ時代 ②アユタヤ時代 ③ラタナコーシン時代の3時代に分けて考察しています。今回は前書きと①のスコータイ時代についてのお話です。

第一章 タイカービングの起源を探る旅:通説の向こう側に見えた真実
ナイフ一本で果物や石鹸に生命を吹き込む芸術、タイカービング。その繊細な美しさに魅了され、日本国内でも数多くの教室で技術を学ぶ人々が増えています。かく言う私もその一人であり、植物が花開く一瞬の煌めきを自らの手で再現できる喜びに、深く心を奪われてきました。
カービングの技術を学ぶ中で、誰もが一度は耳にするのが、その「起源」にまつわる物語でしょう。しかし、タイに長く滞在し、タイ語にも精通している方から「アユタヤ説について書かれた物は実は…」と聞いたことをきっかけに、広く信じられている起源の物語に疑問を抱き、今回の調査を始めることにしました。
タイのフルーツ&ベジタブルカービング、タイ語で「ケ・サラック」(Kaew Sa Lak、แกะสลัก)として知られるこの芸術は、タイを象徴する伝統工芸の一つとして世界的に高く評価されています 。単なる食卓の装飾にとどまらず、タイの宮廷文化が生んだ洗練された芸術形式です 。
しかし、その起源については、長年にわたり複数の説が混在し、歴史的言説は錯綜しています。最も広く知られているのは、約700年前のスコータイ王朝時代(1238年頃-1438年)に、ナン・ノッパマートという名の女性によって始められたという物語です 。一方で、同じく約700年前のアユタヤ王朝時代(1351年-1767年)に宮廷の女性たちによって創始されたとする説も根強く語られています 。さらに、より確実な文献的証拠に基づき、その芸術的洗練が頂点に達したのはラタナコーシン王朝(1782年-現在)、特にチャクリー王朝時代であるとする見解も存在します 。
今回の調査では、これらの相克する起源説を批判的に検証し、伝説と史実を分離しながら、タイのフルーツカービングの真のルーツに迫ります。特に、一般に流布しているスコータイ起源説の中核をなす「ナン・ノッパマートの物語」の信憑性を、現代のタイの学術的研究に基づいて解き明かしていきます。
まずは、今回検証する主要な起源説の概要を以下の表で比較してみましょう。
表1:タイのフルーツカービング起源説の比較分析
| 起源とされる時代 | 中心人物/物語 | 主な典拠 | 現代の学術的評価 |
| スコータイ時代(13-15世紀頃) | ナン・ノッパマートがロイクラトン祭のためにカービングを発明。 | 『ナン・ノッパマートの書』(タムラップ・ターオ・シーチュラーラック) | **低い。**同書は19世紀ラタナコーシン時代の著作であり、ナン・ノッパマートは創作上の人物と見なされている。 |
| アユタヤ時代(14-18世紀頃) | 宮廷の女性/妃(「ターオ・シーチュラーラック」)が伝統を創始。 | 一般的な言説。アユタヤ時代の役職名「ターオ・シーチュラーラック」との混同。 | **低い〜中程度。**精緻なカービングに関する直接的な文献・考古学的証拠に欠けるが、後期にはその萌芽を示唆する文学的記述が存在する。 |
| ラタナコーシン時代(18世紀頃-現在) | 王宮内で芸術として完成され、称賛される。 | 『カープ・ヘー・チョム・クルアン・カーオ・ワーン』(ラーマ2世の王室詩)、宮廷記録、その後の普及。 | **高い。**直接的かつ検証可能な文学的証拠および宮廷生活の記録によって裏付けられている。 |
I. 最も有名な伝説:ナン・ノッパマートとスコータイ起源説は真実か?
A. 起源の物語:ある国民的ロマンス
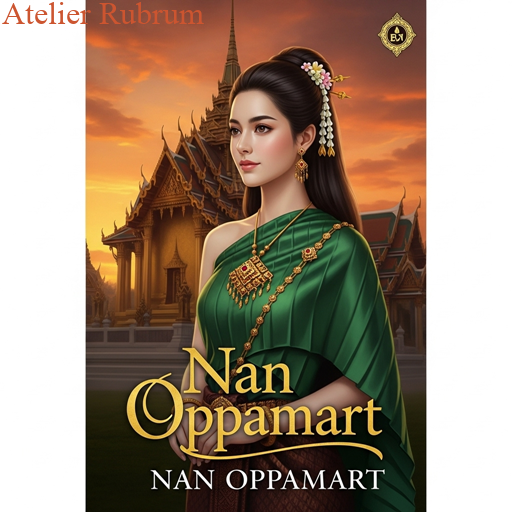
タイのフルーツカービングの起源として最も広く、そして情緒豊かに語られるのが、スコータイ王朝時代に端を発するという物語です。この伝説によれば、13世紀、タイ族最初の独立王朝であるスコータイのプラ・ルアン王(Phra Ruang)の治世に、ナン・ノッパマート(Nang Nopphamat)という名の、美しく才能にあふれた女性がいました 。彼女はバラモン階級の神官の娘で、その聡明さと手先の器用さで知られていたとされます 。
物語のクライマックスは、陰暦12月の満月の夜に行われる「チョン・プリアン」(Chong Priang)という宮廷儀式、すなわち現在のロイクラトン祭(灯籠流し)の前身とされる祭りの場面で訪れます 。王を喜ばせようと考えたナン・ノッパマートは、他の宮廷の女性たちが作る灯籠(クラトン)よりも美しく、独創的なものを作ろうと決意。彼女は、バナナの葉で蓮の花の形をした器を作り、さらにその上に、果物や野菜を用いて鳥や白鳥、様々な動物の形を繊細に彫り上げ、灯籠を華やかに飾り付けたのです 。
この類まれな美しさを持つクラトンは王の目に留まり、深く感銘を受けた王は、これを今後の祭りの手本とするよう命じたと伝えられています 。この物語によって、フルーツカービングは、王への忠誠心と女性の創意工夫から生まれた約700年の歴史を持つ芸術として位置づけられ、ロイクラトン祭の起源とも密接に結びつけられてきました 。
B. 神話の解体:歴史的・文学的精査
しかし、このロマンティックな起源説は、残念ながら現代の歴史学的な精査には耐えられません。タイの歴史学の父と称されるダムロン・ラーチャーヌパープ親王(Prince Damrong Rajanubhab)に始まり、タイ芸術局(Krom Silpakorn)に至るまで、タイの学術界では、ナン・ノッパマートはスコータイ時代に実在した人物ではなく、後世に創作された文学上の登場人物であるというのが定説となっています 。
この伝説の唯一の典拠は、『ナン・ノッパマートの書』、または正式名称を『タムラップ・ターオ・シーチュラーラック』(Tamrap Thao Sri Chulalak)という書物です 。しかし、この書物はスコータイ時代の文献ではなく、ラタナコーシン王朝初期、特にラーマ3世(在位1824-1851年)の治世に執筆または編纂されたものであることが、複数の証拠から明らかになっています 。
その根拠は以下の通りです。
- 言語学的分析:『タムラップ』で使われている語彙や散文のスタイルは、ラームカムヘーン大王碑文や『トライプーム・プラ・ルアン』といった、真作とされるスコータイ時代の文献のそれとは著しく異なります。文章はより流暢で現代的であり、スコータイ時代には一般的でなかった外国(例えば中国)の産物や国々への言及が含まれています 。
- 時代錯誤(アナクロニズム):本書には、13世紀のスコータイには存在しなかった概念や事物に関する記述が見られます。最も決定的なのは、物語の主人公に与えられた称号「ターオ・シーチュラーラック」です。この称号はスコータイの宮廷には存在せず、アユタヤ王朝の宮廷で確立された特定の高位の妃の役職名でした 。スコータイ時代を舞台にした物語にアユタヤ時代の役職名が登場すること自体が、この書物が後世の創作であることを示す強力な証拠です。
C. 神話の目的:教訓と国民的アイデンティティの構築
ナン・ノッパマートの物語が歴史的事実でないとすれば、なぜこのような物語が創作されたのでしょうか。その背景には、19世紀のシャム(タイ)における文化的・政治的要請がありました。
ラーマ3世の治世は、大きな戦争が減り、中国との交易によって商業が繁栄し、国家が安定した時代でした 。このような状況下で、王室はシャムの文化を定義し、保存し、高めることに積極的に関与しました。『タムラップ・ターオ・シーチュラーラック』の創作は、この文脈で理解されるべきです。この書物は単なる物語ではなく、「スパーシット・ソーン・サトリー」(suphasit son satri)、すなわち宮廷に仕える女性たちのための行動規範や教訓書としての機能を持っていたのです 。美貌、知性、芸術的才能、そして王への揺るぎない忠誠心といった、理想的な妃の資質を詳述しており、ナン・ノッパマートはその理想を体現する文学的キャラクターとして創造されました。
さらに重要なのは、この理想的な女性像の物語の舞台を、タイ民族の「黎明期」としてロマンティックに理想化されたスコータイ王朝に設定したことです。これにより、19世紀の宮廷の理想が、タイ最初の王朝にまで遡る古くからの連続した、洗練された王室文化であるかのような物語が構築されました。これは、当時のチャクリー王朝の正統性を強化し、統一された国民的アイデンティティを育むための、意図的な文化的・政治的構築物だったのです。したがって、フルーツカービングの起源をナン・ノッパマートに帰する物語は、歴史的誤謬というよりも、19世紀のシャムにおける国家形成プロジェクトと密接に結びついた創造物なのであると結論付けられます。
と、ここまでが今回の文章です。
あとがきと感想
いきなりスコータイ王朝時代の起源説が否定に近い形で登場して面食らってしまいます。そもそもナン・ノッパマートの物語がカービングの起源説に大きく関わっているとは全くもって知りませんでしたし、この名前自体が初耳でした。せっかくタイ語の読み書きができる生成AIと知り合えたので、この「ナン・ノッパマートの物語」についても調べてまとめてもらいました。これも番外編として投稿したいと思っています。そして本筋とは違う点ですが、タイが昔「シャム」(Siam)と呼ばれていて、シャム猫との名前の由来だと思い出したことがちょっと新鮮でした。

次回はスコータイ起源説の次に知られているアユタヤ起源説についての記述となります。スコータイ起源説がちがうとなるとアユタヤ起源説が有力となるのでしょうか。次回をお楽しみにしてください。
***カービング起源説関係の投稿中に挿入している画像はGoogle AI StudioのImagenで生成したものです***
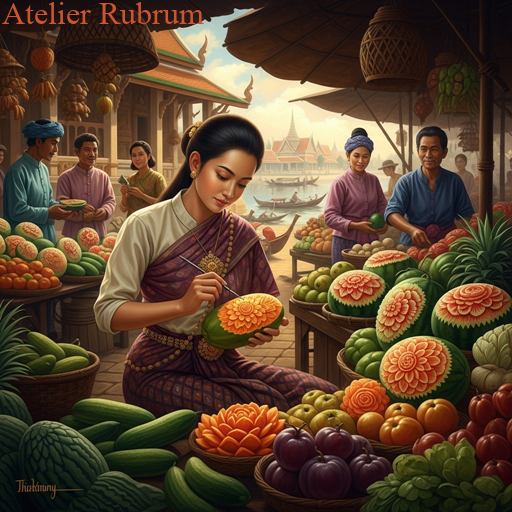
このタッチの画像とか

こんな感じの写真のような画像も生成AIに作ってもらったオリジナル作品です。
ではまた!!





