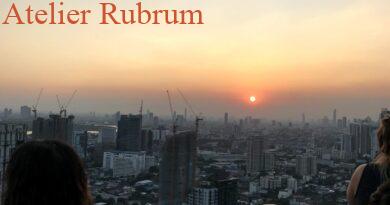カービングの起源を探す旅 アユタヤ起源説編
前回はカービングの起源がスコータイ時代にあるのではないかということについての文章を載せました。日本国内でもこの説が有力だったのであっさり否定された形となり驚きました。となると、次にくるのがアユタヤ起源説ですね。ですが今回もわたし的には意外なお話になっています。というか、短い。全体としては結構薄味の論評となっています。そのため読みやすいとは思います。
それではいってみましょう。

目次
II. もう一つの通説「アユタヤ起源説」の正体
A. 曖昧な主張の評価
スコータイ起源説と並んで広く語られるのが、アユタヤ王朝を起源とする説です 。これらの主張は、しばしば「宮廷の女性たち」や「一人の妃」といった一般的な表現を用い 、スコータイ説と同様に「約700年前」という時間枠を設定することが多く、ラタナコーシン以前の歴史に関する一般的な知識の混乱を示唆しています。アユタヤ説は、スコータイ説ほど具体的な物語を伴わず、漠然とした形で流布しているのが特徴です。
B. 「ターオ・シーチュラーラック」という称号:混乱の源泉
アユタヤ起源説が生まれた背景を解明する上で決定的に重要なのは、「ターオ・シーチュラーラック」という名称の歴史的実態です。前述の通り、これは個人の名前ではなく、アユタヤ王朝の宮廷における高位の妃に与えられた正式な役職名でした 。
歴史的に、この称号は、アユタヤに併合された旧スコータイ(プラ・ルアン)王家の王女に与えられることが多かったとされます。これは、二つの王国がアユタヤの支配下で政治的に統合されたことを象徴するものでした 。歴史上、この称号を持った女性は複数存在し、中にはナーラーイ王の治世に不義の罪で処刑された有名な人物もいます 。
この歴史的事実が、アユタヤ起源説の誕生に深く関わっています。まず、19世紀に書かれた『タムラップ』が、創作上の人物であるナン・ノッパマートに「ターオ・シーチュラーラック」という称号を与えました。一方で、「ターオ・シーチュラーラック」はアユタヤ時代の歴史的な役職名として実在しました。時が経つにつれて、この創作された物語と歴史的な称号が人々の間で混同されるようになったと考えられます。つまり、この称号がアユタヤと関連があることを知っている人々が、広く知られたカービング発明の物語と結びつけ、その物語の舞台がアユタヤであったと誤解するようになったのです。
したがって、「アユタヤ起源説」は、独立した証拠に基づく主張というよりも、19世紀の文学的創作と15世紀から18世紀にかけての実際の宮廷の役職名との間の混同から生じた「歴史的残響」と見なすのが妥当でしょう。
C. 証拠の欠落:「沈黙からの議論」
アユタヤ王朝が木彫や石彫などの高度な工芸の中心地であったことは間違いないものの 、フルーツカービングのような極めて洗練された芸術に関する直接的な証拠は著しく欠けています。この時代のアユタヤ宮廷の生活は、外交官、商人、宣教師といった外国人訪問者によって詳細に記録されており、これらの記録は当時の社会を理解するための貴重な史料となっています 。
これらの記録は、シャムの食文化についても言及しており、魚と米を中心とした質素な食事や香辛料の使用について記述しています 。しかし、これらの詳細な観察記録の中に、後のタイ文学で描かれるような、壮大で芸術的なフルーツカービングに関する記述は知られていません。もしそれが王室の宴席で際立った特徴であったならば、驚きをもって記録された可能性は非常に高いはずです。
この「沈黙からの議論」は、確証ではないものの、一つの強力な状況証拠となります。それは、装飾的な食事の準備は間違いなく存在したでしょうが、「ケ・サラック」という高度に体系化された宮廷芸術としてのフルーツカービングは、ラタナコーシン時代に達するほどの卓越性や形式性をまだ獲得していなかったことを強く示唆しています。アユタヤにおけるその起源は、より萌芽的で非公式なものであった可能性が高いと考えられます。
まとめと感想 (by Rubrum Yoshi)
ここまで歴史的に深掘りすると知らないことばかりで本当に新鮮です。今回特に印象深かった部分は「アユタヤ王朝が木彫や石彫などの高度な工芸の中心地であったことは間違いないものの 、フルーツカービングのような極めて洗練された芸術に関する直接的な証拠は著しく欠けています」と、木彫りや石彫りなど古くから職として確立されていた分野よりもフルーツカービングなどの方が「より洗練されたもの」として扱われているところです。現代でも「職業」または「商売」として、「趣味」としてでもソープ、フルーツ、ベジタブルカービングよりも木彫りや石彫り分野の方がメジャーな印象がありますから、このような扱いを受けるととてもうれしく感じました。
そしてスコータイ起源説に続いてアユタヤ起源説も簡単に否定されてしまいました。「歴史的残響」というきつい言葉を使って、「アユタヤにおけるその起源は、より萌芽的で非公式なものであった可能性が高いと考えられます」と締めくくられているように、実はこの後に続く時代にカービングの分野が確立されていったのかもしれません。とはいえ、やはり物事の起源といえばより古い方がありがたく思う面もあります。そういったことからこれまでの説が通説として大きくなっていったのかなと思いました。ロマンですね。

次回は最終回です。AIさんらしく確かな記録を探して検証していきます。これがいちばん欲しかった情報です。一時情報的な部分ですね。アユタヤ以降の時代に起源らしき物は見つかるのか。最後はロマンのある話になっていますのでお楽しみに!