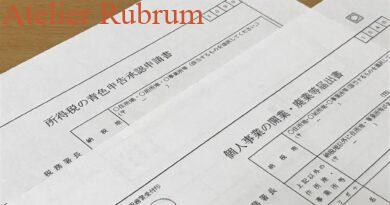タイの古典『タムラップ・タオ・シーチュラーラック』通称『ナーング・ノッパマートの書』について②
今回は第一回「序章 - 宮廷の華、ナーング・ノッパマートの物語」に続いて、第二回「宮廷女性の作法と教養 - 理想の女性像を求めて」になります。今時ですとコンプラに引っかかりそうな怖さもありますが、
「原作が発表された当時の時代背景と作品のオリジナリティを尊重し、今日の基準では不適切と思われる表現も、原作のとおりとしております。ご了承ください。」寛大な気持ちでお読みください。
「この後、スタッフがおいしくいただきました。」でも大丈夫です。
感想などは最後に追記しています。ではどうぞ。

目次
第2回:宮廷女性の作法と教養 – 理想の女性像を求めて
『タムラップ・タオ・シーチュラーラック』が後世に与えた最も大きな影響は、その核心部分をなす、宮廷に仕える女性、特に王の寵愛を受ける側室たち(นางสนมกำนัล)が、いかにして自らを律し、王と国家に貢献すべきかという、厳格かつ美しい行動規範を体系的に示した点にある 。この書は、ナーング・ノッパマートという理想的な女性像を鏡として、当時の人々が考える「完璧な女性」の姿を、具体的な行動指針と共に描き出している。
物語の中で、ノッパマートが宮廷に上がる前夜、父であるプラ・シーマホーソットと母レワディーが娘に与える教えは、この書の思想的根幹をなす、極めて重要な場面である 。彼らは、外面的な美しさだけでは王の寵愛を長く保つことはできないと説き、真の価値は内面から滲み出る知性と徳、そして他者への配慮にあると教える。この教えは、単なる親子の会話に留まらず、宮廷という特殊な社会で生き抜くための、実践的な哲学として語られる。
理想の宮廷女性に求められる資質
この書が示す理想の女性像は、現代の我々が見ても感嘆するほど多角的であり、主に以下の三つの柱から成り立っている。
貞淑と忠誠:王への絶対的な献身
宮廷女性にとって最も根源的な徳目は、王に対する絶対的な忠誠心と貞淑さである。この書は、自らの行動の一つ一つが、常に王の名誉と王国の威光に繋がるべきであると繰り返し説く。ノッパマートの振る舞いは、王の寵愛を独占しようとする個人的な欲望や嫉妬からではなく、王に仕える者としての公的な責任感から生まれるものとして、一貫して描かれている 。例えば、他の側室たちとの関係については、「決して他者を妬まず、自らの行いを正し、徳を磨くことで、自然と人々の尊敬を集めるべきだ」と説く。これは、個人の感情よりも公の秩序と調和を重んじる、宮廷社会の厳格な価値観を色濃く反映している。
深い教養と知性:王の良き相談相手として
ノッパマートは、ただ美しいだけの女性ではない。彼女は、世界の成り立ち、諸国の言語、仏教の深遠な教え、そして国家儀礼の基礎となるバラモン教の儀式に至るまで、幅広い知識を持つ、極めて知的な女性として描かれている 。特に、バラモン教の儀式に関する深い知識は、宮廷の公式行事を滞りなく、かつ荘厳に執り行う上で不可欠な教養であった 。この書は、女性がその美しさだけでなく、知性によっても自らの地位を確立し、時には王の良き相談相手となり、政治的な助言さえも行い得る存在であることを示唆している。これは、女性の役割を単なる装飾品としてではなく、国家運営の一翼を担う重要な存在として捉える、先進的な視点とも言える。
卓越した芸術的才能(วิชาการช่างสตรี):文化の創造者として
この書が最も多くのページを割き、生き生きとした筆致で語るのが、「女性の工芸技術」の重要性である 。美しい花飾りを作る繊細な指先、賓客をもてなすための供物台(พานหมาก)を飾り付ける洗練された美的センス、そして後にカービングの起源として伝説となる灯籠(กระทง)を創作する比類なき独創性。これらは、単なる手慰みや個人的な趣味ではない。王を楽しませ、宮廷生活に彩りを与え、国の文化レベルの高さを内外に示すための、極めて重要な政治的・文化的な営みとして位置づけられているのだ 。ノッパマートの創造性は、彼女が数多いる側室たちと一線を画し、王から特別な寵愛と尊敬を勝ち得る決定的な要因となる。彼女は、文化の消費者であるだけでなく、新たな文化を創造する主体的な存在として描かれているのである。
『タムラップ・タオ・シーチュラーラック』が描く理想の女性像は、現代の価値観から見れば、窮屈で封建的に感じられる部分もあるかもしれない。しかし、それは同時に、女性が自らの知性と才能を最大限に発揮し、厳格な社会規範の中で自らの価値を証明し、尊敬を勝ち取っていくための、力強い生存戦略の書でもあった。この指南書は、後の時代の女性たちにとって、宮廷という特別な世界で生きるための、そして理想の女性として社会的に認められるための、貴重な道しるべとして、長く読み継がれていくことになったのである 。
終わりに
「決して他者を妬まず、自らの行いを正し、徳を磨くことで、自然と人々の尊敬を集めるべきだ」という部分は仏教的なんでしょうね、私は、なんちゃってではありますが仏教徒ですのでとても強く賛同できる部分です。物語は13~15世紀の物とされていますが、この物語が創られた(創られたと言い切ってしまいますが)のは19世紀前半である説が有力とのことで、本当に昔からずっとこの思想だったかはもはや分かりようがありません。ですが、仏教徒にはわかりやすい考え方ですよね。それが簡単にはできないのがツラいところですが。
そして「後にカービングの起源として伝説となる灯籠(กระทง)を創作する比類なき独創性」と、ここでもカービングの起源はこの辺である的な記述がありますね。この投稿を創るにあたり物語を何度も読み返しているうちに、これまで全く知らなかった上に最初は軽い興味しか無かったナーング・ノッパマートの世界観に自分が結構深くハマっているとに気づいてきました。

でもやっぱりいまではLGBTQ+やフェミニズムの観点からは怒られそうですね。今回のブログ投稿作成に当たり、自分の立場を伝えるにはどうするかとAIさんに聞いてみたら以下の文言を作ってもらえたので最後にもう一度貼り付けますね。今回はここまでです。長い文章を最後までお読みいただきありがとうございました。
この物語が生まれた時代には、まだ現代のように多様な性のあり方(LGBTQ+)に関する理解が一般的ではありませんでした。
そのため、登場人物たちの言動には、「女性は女性らしく」といった描写や、男女の役割を固定的に捉えるような部分が見られます。
このブログでは、そうした点も一つの時代性として捉え、作品の魅力と共に紹介していきたいと考えています。現代の私たちの視点とは少し違う世界を、どうぞお楽しみください。